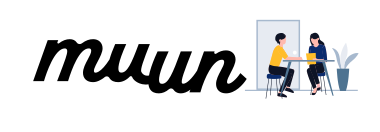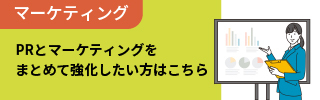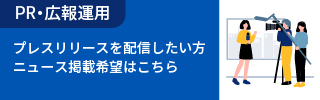2025年最新版|オンラインと地域連携で患者さんに選ばれるクリニック集客ガイド
2025/04/11
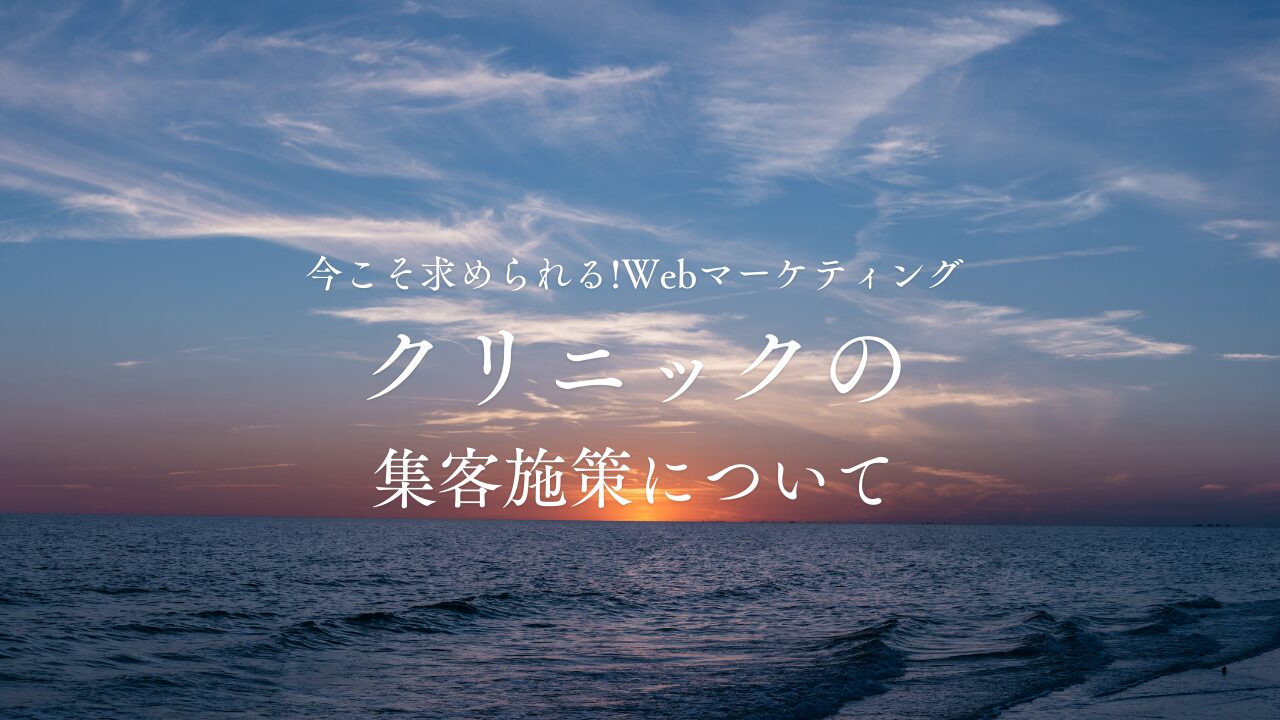
都市部・地方を問わず医療機関の競争は激化しており、患者さんが「どのクリニックを選ぶか」を慎重に比較・検討する時代に入りました。特に、スマートフォン検索の普及やSNSの活用、口コミサイトの充実により、患者さんが情報を得るハードルが大きく下がっていることが背景にあります。
実際、2025年初頭の国内調査では、「気になる症状があればまずスマホで調べる」「口コミや評価を確認してから予約する」と答えた人が7割を超えており、特に20〜40代を中心にその傾向が顕著です。
一方、クリニックを取り巻く環境も大きく変化しています。診療報酬改定や地域包括ケアの推進、かかりつけ医機能の明確化により、医療サービスの多様化と経営課題の複雑化が進んでいます。今や「ただ待っているだけで患者が来る」時代ではありません。
本ガイドでは、オンラインとオフラインの施策を掛け合わせた最新の集客手法に加え、院内オペレーション、スタッフ教育、地域との連携など、クリニック経営で実践すべきポイントを12章にわたって紹介します。マーケティングに不慣れな方でも実行できるよう、成功事例や具体的なノウハウを交えながら、「患者さんに選ばれるクリニック」をつくるための実践ガイドとしてお届けします。
1.医療マーケットの現状と患者行動の変化
厚生労働省の最新統計(2024年末時点)によれば、全国の一般診療所数は約10万施設とほぼ横ばい。ただし「かかりつけ医を持たない層」が増加しており、必要なときにネット検索でクリニックを探す行動が一般化しています。
スマートフォン利用者のうち約8割が「身体の不調を感じたら、まずはネットで検索する」と回答。その際には、Googleマップや医療ポータルサイト(ホスピタ・エキテン・Calooなど)に加え、InstagramやYouTubeといったSNSも参考にするケースが増えています。とくに20〜30代は「知らない土地でも高評価のクリニックを選ぶ」傾向が強く、口コミ評価が3.5未満だと来院を避ける人も少なくありません。
こうした状況から、もはや「駅近に看板を出していれば自然と患者が来る」時代ではありません。オンラインでの情報発信と評価管理がますます重要になる一方で、地域の信頼を得るためのオフラインの取り組みも引き続き不可欠です。
デジタル×リアルの両軸で信頼と集客を積み上げる――そのバランスをうまく整えたクリニックが、今後さらに選ばれていくことは間違いありません。
クリニック向けのPEST分析を表形式でまとめました。
PEST分析とは、政治(Political)・経済(Economic)・社会(Social)・技術(Technological)の4つの観点から、外部環境を把握するフレームワークです。
地方クリニックにおけるPEST分析(2025年版)
| 要因 | 内容(外部環境) | クリニックへの影響 |
|---|---|---|
| P:政治的要因 | ・診療報酬制度の改定(在宅医療・慢性疾患管理への重点化) ・地域医療構想の推進・再編 ・医療DX推進(電子カルテ・オンライン診療の導入支援) | ・収益構造や診療内容の見直しが必要に ・他機関との連携強化が求められる ・ICT導入による差別化・効率化が進む |
| E:経済的要因 | ・地方における人口減少・少子高齢化 ・地域経済の停滞、所得格差の拡大 ・エネルギー・人件費の高騰 | ・外来患者数の減少リスクあり ・高齢者医療・在宅医療ニーズは増加 ・経営の効率化・コスト最適化が不可欠 |
| S:社会的要因 | ・患者層の多様化(高齢者・外国人・若年層など) ・医療リテラシーの格差 ・SNS・口コミの影響力拡大 | ・わかりやすい説明や接遇力が重要に ・Web・SNSを使った信頼構築が必須 ・地域活動や教育啓発の取り組みも有効 |
| T:技術的要因 | ・オンライン診療や遠隔モニタリングの普及 ・予約システム・Web問診・LINE通知などの活用 ・生成AIやチャットボットによる業務支援 | ・患者利便性の向上で差別化が可能 ・スタッフ業務の効率化と時間短縮に貢献 ・デジタル対応できるかどうかが競争力に直結 |
2.戦略設計――ペルソナと差別化を明確にする
2-1. ペルソナ設計
多くのクリニックでは「誰でも受け入れる」という方針を掲げていますが、実際には患者さんの年代や生活スタイル、通院理由、情報収集の手段は千差万別です。
そこで欠かせないのが「ペルソナ」の設定です。
例として以下のような想定が考えられます。
- 20代女性/美容皮膚科に関心/Instagramで症例検索
- 60代男性/生活習慣病管理が目的/家族の勧めで来院
- 40代女性/仕事帰りに通いたい/夜間診療・駅近を重視
このように具体的な人物像を複数パターン設定することで、診療内容・発信方法・接遇など、すべてのタッチポイントを最適化できます。とくにSNSの影響力が強い診療領域(美容・メンタルヘルス・小児科など)では、ペルソナに合わせた戦略が成果を左右します。
2-2. USP(独自の強み)の言語化
「どこにでもあるクリニック」ではなく、「このクリニックに行きたい」と思われるためには、独自の強み(USP)を明確に言語化し、わかりやすく伝える必要があります。
例:
- 「高血圧・糖尿病など生活習慣病をワンストップで管理」
- 「土曜日もCT検査可能」
- 「小児科・皮膚科・予防接種を1つの施設で完結」
USPはWebサイトやSNSのプロフィール、診察券、名刺などあらゆる接点に統一して表示するのがポイントです。「このクリニックといえば〇〇」というイメージが記憶に残りやすくなります。
3. オンライン施策① ― SEO・MEOで“探している患者”を逃さない
3-1. SEO対策のポイント
1. 症状名+地域名をタイトルに入れる
例:「【医師監修】◯◯市で大人ニキビを治す5つの方法」など、患者さんが実際に検索するキーワードをタイトルに入れることで、検索流入が増加します。
特に「症状+クリニック名」「駅名+診療科」は効果的です。
2. FAQを見出し(h2・h3)に設定
音声検索やロングテールキーワードに対応するため、「◯◯は何科を受診すればいい?」「予防接種はいつから可能?」など、患者さんの疑問をそのまま見出しに使いましょう。
3. E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を高める
医師の資格、学会発表、受賞歴、メディア掲載などは、Webサイト上で明示しましょう。
「医師紹介」や「実績」ページに信頼できる情報を掲載することで、Googleの評価が上がります。
4. 画像のalt属性を適切に設定
院内設備や診察風景などの画像には「外来診察室」「エコー機器」など、具体的な説明文をalt属性に記述。SEO効果に加え、アクセシビリティ向上にもつながります。
3-2. MEO対策(Googleマップでの上位表示)
1. Googleビジネスプロフィールの情報充実
診療時間・電話番号・診療科目・Webサイトなど、基本情報を正確に記載し、750文字以内で強み(USP)も明記しましょう。
2. 写真や360°ビューを活用
受付・待合室・診察室・医療機器など、安心感が伝わる画像を定期的に追加します。360°ビューがあると来院前の不安軽減にもつながります。
3. 口コミ管理を丁寧に
好意的な口コミにはお礼を、ネガティブな意見にも礼儀正しく事実確認・改善の姿勢を示すことで「誠実なクリニック」として印象付けられます。
4. オンライン施策② ― Webサイトと予約導線の最適化
4-1. Webサイトの構成と表現
1. ファーストビューに診療内容とアクセス情報を明記
「内科・小児科・予防接種」などの診療科目と「駅徒歩3分・駐車場10台完備」などの利便性は、スクロール不要で確認できる位置に配置。
初診予約ボタンも目立つ位置に設置し、迷わず予約まで進めるようにします。
2. Web問診の導入で受付業務を効率化
来院前にスマホから問診票を入力してもらうことで、受付・診療の準備がスムーズになります。電子カルテとの連携で更に時間短縮が可能です。
3. FAQページの充実
「予防接種は保険適用?」「診察料の目安は?」「駐車場はありますか?」など、よくある質問を整理することで電話対応の負担も軽減。
サイトを見た人に「わかりやすくて親切なクリニック」という印象を与えます。
5. オンライン施策③ ― SNSでブランドの信頼を育てる
5-1. Instagram活用
- 美容皮膚科や小児科など、視覚で伝わる科目と相性抜群
- 術前・術後の症例投稿は、ガイドライン遵守と正しい副作用説明が必須
- ストーリーズに「質問箱」や「投票機能」を活用すれば、フォロワーとの交流が活性化し、投稿のリーチが伸びやすくなります
5-2. YouTube運用
- 「1分でわかる花粉症の対処法」「30秒でできる腰痛予防ストレッチ」など、短尺・専門的な動画はブランディング効果が高い
- 動画概要欄にタイムスタンプや予約リンクを入れることで、視聴者の行動を促しやすくなります
5-3. LINE公式アカウントの活用
- 予約前日のリマインド通知 → キャンセル防止
- 検査結果通知やワクチン接種の案内 → 利便性向上
- 食事アドバイス・季節の健康情報 → 継続的な関係づくり
6. 広告運用 ― 打つときには“法令遵守”を最優先に!
患者さんにクリニックの存在を知ってもらう手段のひとつに「広告」がありますが、医療機関においては他業種と異なり、広告に関する法律・ガイドラインが非常に厳しく定められていることに注意が必要です。
6-1. 医療広告は「何でも出せるわけではない」
医療機関の広告は、医療法・医療広告ガイドラインに基づき、表示できる内容に明確なルールがあります。
たとえば、次のような表現は原則禁止とされています。
- 「地域No.1」「必ず治ります」などの優良誤認や誇大表現
- ビフォーアフター写真や患者の体験談(たとえ本人の感想であっても)
- 院長やスタッフによる推薦コメント・ランキング表示
これらは、患者さんに誤解を与える可能性があるとしてNGとされており、うっかり掲載してしまうと行政指導や指摘を受けるリスクがあります。
6-2. オンラインの情報発信も“広告扱い”になることがある
一見広告に見えないようなWebサイトやSNSの投稿でも、「患者さんを誘導する意図があり、診療内容について掲載している場合」は“広告とみなされる”ことがあります。
そのため、自由診療の紹介やキャンペーン告知などを行う際は、特に注意が必要です。
- 治療名だけでなく、リスク・副作用・費用などを正確に表示する
- 表現に主観が入っていないか見直す(「安心・安全」「丁寧な診療」は要注意)
- 定期的に厚生労働省のガイドラインや都道府県の指導内容を確認する
6-3. 伝え方を工夫すれば、十分に魅力を届けられる
広告規制があるからといって、何も伝えられないわけではありません。
患者さんにとって有益な情報を、正確かつ誠実に発信することは大切です。
- 医師のプロフィールや資格・所属学会
- 診療時間・診療科目・設備情報
- 健康に関するコラムやFAQ形式の記事
- 院内の雰囲気を伝える写真やお知らせ
などは、法的に問題のない範囲で、十分な情報提供手段となります。
6-4. 不安なときは専門家に相談を
広告や表現に迷った場合は、医療広告の専門コンサルタントや行政機関(保健所など)に事前に相談することをおすすめします。
実際、細かい表現や掲載方法に関しては、各都道府県ごとに判断が異なるケースもあるため、慎重な対応が求められます。
広告は「打てるかどうか」より「適法に打てるか」が重要
正確で誠実な情報発信が、結果的に患者さんとの信頼を築く一番の近道です。医療広告ガイドライン対応|事前確認チェックリスト(2025年版)
項目 チェック内容 ✅OK / ❌要修正 備考 1. 基本情報 医療機関名・所在地・診療科目・診療時間など、事実に基づいた内容のみ記載している ✅ / ❌ 誇張なし、虚偽なし 2. 禁止表現の回避 「必ず治る」「日本一」「安心・安全」などの誇大・優良誤認表現を使っていない ✅ / ❌ 主観的・断定的な表現はNG 3. 比較・誘引表現の確認 他院との比較(例:「当院は他院より〇〇が優れている」)を含んでいない ✅ / ❌ 比較データも基本NG 4. 治療実績の掲載 実績は正確な数値・期間で表示し、誇張や不明確な文言を使っていない ✅ / ❌ 「多数の実績」→要注意 5. 自由診療の記載 自由診療については、費用・リスク・副作用・治療期間を具体的に記載している ✅ / ❌ 必須4点セットを明記 6. 患者の声・体験談 口コミ・体験談(患者本人の発言含む)は掲載していない ✅ / ❌ 医療機関側の紹介も不可 7. ビフォーアフター 治療前後の写真は使用していない ✅ / ❌ 審美・美容系でも原則NG 8. 医師の紹介 氏名・資格・所属学会等を事実に基づき記載している ✅ / ❌ 「○○学会専門医」はOK(条件あり) 9. SNS・Webでの表現 投稿に「誘引目的」や「診療内容の詳細」が含まれていない、もしくは内容が適切である ✅ / ❌ SNSでも広告扱いになる可能性あり 10. 最新ガイドラインの確認 厚生労働省・都道府県の最新指針を確認済み ✅ / ❌ 年1回以上の確認が推奨 7. オフライン施策と地域連携 ― 地元での信頼を積み重ねる
オンライン施策が重要視される一方で、地域に根ざした信頼づくりは今も昔も変わらず大切です。特に高齢者やネットに慣れていない層にとっては、リアルな接点が来院のきっかけになることも多く、地域とのつながりが強いクリニックは紹介やリピートにもつながりやすい傾向があります。
7-1. 調剤薬局との連携
- 院内に地域薬局のチラシを設置、または自院の案内を薬局に置いてもらうなどの相互送客
- 「このクリニックで出された薬をもらった」「薬剤師に勧められた」などが来院動機になるケースも
7-2. 企業との健康支援連携
- 地元企業と連携し、産業医契約・健康セミナーの開催などで関係性を築く
- 企業内での健診後にフォロー診療として受診が促されるなど、BtoB的な導線が可能
7-3. 学校・地域団体との協力
- 小中学校での健康講話やPTA主催イベントに参加
- 地域の保育園や町内会と連携して「子育て相談会」や「高齢者向け健康教室」を開催する例も
- 顔の見える関係性が“選ばれる”理由になる
7-4. 院内セミナー・地域向けイベントの実施
- 「糖尿病と食事」「花粉症対策セミナー」「離乳食講座」など、専門性を活かした小規模セミナーを定期的に開催
- 既存患者のロイヤルティ向上だけでなく、新たな来院動機のきっかけづくりにも
8. 患者体験(PX)を高め、リピートを促す
PX(Patient eXperience)=患者さんが通院を通して感じる「体験価値」を向上させることは、リピート率や口コミ評価、紹介数の向上に直結します。
8-1. 待合環境の最適化
- 混雑状況の見える化(モニター・LINE通知など)で不安と不満を軽減
- 快適な空間づくり(照明、空調、BGM、雑誌など)によってストレスを最小限に
8-2. キャッシュレス対応の推進
- クレジットカード・交通系IC・QRコード決済などを導入することで会計時間を短縮し、通院の負担を軽減
- 若年層・ビジネスパーソンにとっては利便性の高い選定要因にもなる
8-3. アフターフォローの充実
- 診察後にLINEやメールで次回来院の案内・健康アドバイスを配信
- 特に慢性疾患の患者さんには、定期的なコミュニケーションが「忘れずに通える安心感」に
9. スタッフ教育と院内オペレーションの最適化
患者さんが感じる満足度の多くは「医師の腕」だけでなく、受付・看護・電話応対・全体の連携力に左右されます。
だからこそ、チームとしての対応品質を統一することが信頼につながります。
9-1. 接遇・電話応対のマニュアル化
- 初診対応、再診案内、よくある問い合わせなどをフロー化・スクリプト化
- 医療現場では言葉遣いや声のトーンも印象を左右するため、具体的な言い回しのテンプレートを共有しておくと効果的
9-2. ロールプレイ研修の実施
- 月1回、短時間でもよいのでスタッフ同士でロールプレイを行い、接遇品質をブラッシュアップ
- 想定問答を実際に声に出して練習することで、自然な応対ができるように
9-3. オペレーションの見直し
- Web問診・電子カルテ・自動精算など、導入して終わりではなく、実運用に合わせた最適化を
- 混雑時でも流れが滞らないよう、診療前後の段取り・役割分担を明確にすることがカギ
10. KPIとダッシュボード運用 ― 集客を“見える化”して改善につなげる
感覚や経験だけに頼るのではなく、集客を「数字」で捉える仕組みづくりは、継続的な改善とスタッフ間の共有に欠かせません。KPI(重要業績評価指標)を明確にし、定期的に振り返ることで「うまくいっていること」と「改善すべきこと」がはっきり見えてきます。
10-1. クリニックで活用すべき主なKPI例
10-1. クリニックで活用すべき主なKPI例
| 指標名 | 内容 |
|---|---|
| 新患予約数 | 月間の初診予約数、または問い合わせ数と来院数の差分をチェック |
| リピート率 | 初診後の再診来院率。慢性疾患などでの定着度の指標として重要 |
| キャンセル率 | 予約数に対して実際に来院しなかった件数の割合。リマインド施策と関係性あり |
| 平均診療単価 | 1人あたりの平均診療収益(自費診療・検査・処方など含む) |
| 口コミ評価 | Googleマップやポータルサイトにおける星の数・件数・内容の傾向を定点観測 |
| MEO表示回数 | Googleビジネスプロフィールの検索インプレッション数。地域での認知度の指標に |
10-2. ダッシュボードで“誰でも見える化”
- Googleアナリティクス、Googleビジネスプロフィール、予約システムなどのデータを Looker Studio(旧:データポータル)で一元管理
- 月1回の定例ミーティングで、KPIの進捗と改善点を共有
- スタッフ全員が「数字を使って会話できる」状態を目指す
10-3. PDCAを継続する体制をつくる
- 例:「検索流入が減少 → SEO記事のタイトル見直し」
「リピート率が低下 → 再診リマインドの頻度変更」など - 改善アクションを試し、再度データで効果検証する流れを習慣化すれば、集客もリピートも安定してきます
11. 成功事例に学ぶ ― 地域で選ばれるクリニックの工夫
11-1. 皮膚科A院|Instagram活用で若年層の新患が30%増
- 医師本人が週3回ペースで治療の考え方や生活アドバイスを投稿
- ストーリーズでの質問返答やDM対応により、信頼と距離感の近さが強みに
- 開設半年でフォロワー8,000人超・新患数が前年比130%に
11-2. 内科B院|口コミ返信で星評価3.9→4.4へ改善
- Googleマップの口コミに対し、スタッフ全員で分担し丁寧に返信
- ネガティブな内容にも真摯に対応し、信頼感を醸成
- ルート検索数が2倍になり、予約件数も1.6倍に増加
11-3. 整形外科C院|YouTubeで地域外からも問い合わせ増
- 理学療法士が出演する「膝痛予防エクササイズ」などの1分動画を投稿
- 「こんなに分かりやすく解説してくれるなら診てもらいたい」と遠方からの問い合わせが急増
- 手術相談件数が1.5倍に増加
12. ロードマップと今後の展望 ― 継続的な成長を仕組み化する
すべてを一度に完璧に進める必要はありません。段階的に無理のないスケジュールを立て、確実に実行することが成長の近道です。
12-1. クリニック集客ロードマップ(目安)
12-1. クリニック集客ロードマップ(目安)
| 時期 | 主な取り組み内容 |
|---|---|
| 1か月目 | – WebサイトとGoogleビジネスプロフィールの整備 – 診療内容やスタッフ紹介ページの更新 – 院内掲示やパンフレットとの情報統一 |
| 2〜3か月目 | – SNSアカウントの開設(Instagram、LINEなど) – 投稿方針・頻度の決定、投稿テンプレートの整備 – よくある質問(FAQ)やコラム記事の準備 |
| 4か月目以降 | – 地域連携の強化(薬局・学校・企業との連携) – 院内イベントやセミナーの企画・実施 – MEOや口コミの定期チェック・返信ルールの整備 |
| 6か月目以降 | – オンライン診療や遠隔モニタリングの導入検討 – スタッフ向け研修制度やマニュアルの見直し – AIや自動化ツールの活用による業務効率化 |
12-2. 今後の展望
- 高齢化の進行により、地域密着型の“通いやすさ”と“フォロー体制”がより重視される時代へ
- 医療と福祉の連携、教育・子育てとの接点など、クリニックの役割が多様化
- 医師一人ではなく、スタッフ全員が“クリニックの顔”として機能する組織力が鍵に
クリニックの集客は、単に患者数を増やすだけではなく、「選ばれる理由」をつくり続けることが本質です。情報があふれる現代において、患者さんは自ら調べ、比較し、信頼できる医療機関を選ぶ時代になりました。
このガイドで紹介したように、WebサイトやSNS、Googleビジネスプロフィールなどを活用して、患者さんにとって役立つ情報を丁寧に発信することが信頼獲得の第一歩です。同時に、地域との連携や院内オペレーションの見直しを通じて、来てくれた患者さんに「ここに通いたい」と思ってもらえる体験を提供することが、再来・紹介につながる好循環を生み出します。
特別な広告予算がなくても、小さな工夫と継続的な改善で成果を出すことは可能です。大切なのは、スタッフ全員で「どうすればもっと喜ばれるか」を考え、実行し続けること。その積み重ねが、地域で必要とされるクリニックへと成長させてくれます。
このガイドが、患者さんの笑顔と健康を支える皆さまの取り組みに、少しでも役立つことを願っています。
できるところから、今日から。まずは一歩、踏み出してみてください。