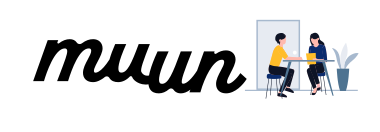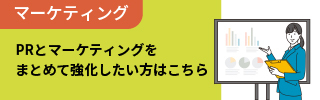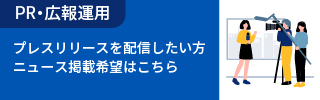SNS全盛期の時代に“地味な広報”は意味がない? プレスリリースの意外なチカラとは
2025/03/21

「プレスリリースはもう意味がない」「SNSがあるからプレスリリースなんて不要」——このような声が近年増えているのは事実です。特にX(旧Twitter)、Facebook、Instagram、TikTokといったSNSが台頭し、情報伝達のスピード感や拡散力、そして双方向性が重視されるようになった昨今、従来から存在するプレスリリースが果たしてどこまで有効なのか、疑問を抱く方も少なくありません。さらに、企業や組織によっては実際にプレスリリースの配信をやめる、あるいは広報活動そのものを大きく転換する動きも見られます。
しかし、本当にプレスリリースは「時代遅れ」であり「意味がない」ものになってしまったのでしょうか。事実を掘り下げてみると、プレスリリースが果たす役割は決して小さくなく、むしろSNSやデジタルメディアと組み合わせることで、より大きな相乗効果を得られる可能性があるのも事実です。この記事では、「プレスリリースってもう意味ないんじゃない?」と言われるようになった背景や、その理由、そして今の時代に合ったPR戦略とどのように組み合わせていけばいいのかを、わかりやすくまとめてご紹介します。
企業や団体の広報担当者の皆さま、あるいは個人事業主やフリーランスとして発信力向上を目指す方に向けて、プレスリリースを正しく理解するための資料としてお役立ていただければ幸いです。ぜひ最後までご覧いただき、SNS全盛時代における効果的な情報発信のヒントを見つけてください。
1.プレスリリースとは何か、そしてその「意味がない」という議論の背景
プレスリリースは企業や団体が公式に発表する文書であり、メディア関係者に対して新情報を伝えるために利用されるものです。伝統的には新聞社、雑誌社、テレビ局といった大手メディア宛に、ファックスや郵送で送付される手法が一般的でした。その後、インターネットの普及に伴い、メール配信やプレスリリース配信サービスが登場し、情報伝達のスピードは一段と加速しました。
ところが、SNSの台頭により、企業や個人がメディアを介さず直接ユーザー・消費者に情報を届けることができるようになりました。さらに、多くの人がスマートフォンを通じて日常的にSNSを利用し、リアルタイムで情報をチェックする時代です。こうした状況下で、わざわざプレスリリースを作成し、配信リストを管理し、メディア関係者に情報を届ける作業は、コストや手間に見合わないのではないか、あるいはメディアよりもSNSで拡散させた方が効果的なのではないか、という見方が出てくるのは自然な流れとも言えます。
また、「プレスリリースを出してもメディアが取り上げてくれない」「プレスリリースの効果測定が難しい」「一方的な情報発信で、対話性に欠ける」という声も聞かれるようになりました。こうした要因が積み重なり、「プレスリリースなんて意味がない」「時代遅れでコスパが悪い」と言われるようになったのです。しかし、実際にそれは事実なのでしょうか。まったく効果がないのであれば、プレスリリースという手法はすでに消滅しているはずですが、依然として多くの企業や団体がプレスリリースを発行し、一定の成果を上げているケースも少なくありません。
2.プレスリリースが「意味がない」と言われる具体的な理由
2-1. 拡散力の低下
かつてはプレスリリースが主要メディアに取り上げられれば、不特定多数への拡散効果は絶大でした。しかし近年では、情報源があまりにも多様化し、ひとつのメディアだけに依存する時代ではなくなっています。特定の新聞社やテレビ局が取り上げたとしても、ターゲット層によっては届かないこともあります。そのため、「どれだけプレスリリースを出しても、思ったほど拡散されない」という印象を抱く企業が増えています。
2-2. SNSによる直接的な発信の強化
SNSが普及したことで、企業や個人はダイレクトに情報を届けられるルートを手にしました。X(旧Twitter)やInstagramなどは拡散性が高い上に、いいねやリツイートといった形でユーザー同士が口コミを発生させるため、プレスリリース以上に実際の顧客やファンに届きやすいというメリットがあります。こうした状況から、SNSを重視すればプレスリリースは不要ではないか、と考える人が増えました。
2-3. コストパフォーマンスの問題
プレスリリースを作成するのには時間と労力がかかります。文章構成を考え、デザインを調整し、配信リストを整え、送付後のフォローアップを行うなど、多大な手間とコストが発生します。それに対し、SNSであれば比較的手軽に投稿を作成でき、画像や動画も瞬時にアップロードできます。その手軽さと比較して「プレスリリースはコスパが悪い」と感じる人もいるでしょう。
2-4. メディアが取り上げるハードルの高さ
プレスリリースを送ったからといって、必ずメディアに取り上げてもらえるわけではありません。ニュース性が低いと判断されれば、メディア側からスルーされることも多いです。とくに話題性のない内容や似たようなリリースが乱発される状況では、埋もれてしまうリスクも高まります。「出しても載らないなら意味がない」と感じる人が増えるのも無理はありません。
3.プレスリリースは本当に不要なのか? 依然として残る価値
これまで挙げたように、プレスリリースの有効性を疑問視する声には一理あるでしょう。しかし、同時にプレスリリースには独自の価値が依然として存在します。プレスリリースがSNSに比べてまったく劣っているわけではなく、それぞれのメディアの特性を活かした使い分けや併用が重要です。
3-1. 信頼度の担保とオフィシャル感
SNS投稿は企業や個人が直接発信するため、どうしても「宣伝色が強い」という印象を拭いきれません。一方で、プレスリリースはメディア向けの公式文書という体裁を持ち、客観的な情報伝達という側面が強調されます。メディアがプレスリリースを取り上げた場合、第三者の目を通して情報が発信されることになり、受け手にとっては“報道”としての重みが増すという利点があります。
3-2. 大手メディアへのアプローチ
SNS拡散だけではリーチできない層や、一定の信頼を持たれた大手メディアの力を借りたい場合、プレスリリースは今でも有力な手段です。特に新聞社やテレビ局といった巨大メディアは、企業や団体が発表するプレスリリースを日常的にチェックしています。そこで目に留まれば、SNSの拡散だけでは得られない大規模な波及効果が見込めます。
3-3. 企業や組織の内部統制や情報整理
プレスリリースを作成する過程で、社内の関係者が情報を精査し、内容を正確にまとめる必要があります。これは一種の「公式発表としての情報整理」のプロセスであり、SNS投稿のようにフットワーク軽く手軽に情報発信するのとは異なるメリットがあります。記者やメディア関係者の目を意識した文書を整備することで、組織としてのコンプライアンスやメッセージの整合性を保ちやすくなります。
4.プレスリリースとSNSの相互補完関係
「プレスリリース vs SNS」という対立構造で議論されることが多いですが、実際には両者を相互に補完するアプローチが効果的です。具体的な組み合わせ方としては、以下のような点が挙げられます。
4-1. プレスリリース後のSNS拡散
プレスリリースを出した直後に、SNSを活用して「公式リリースが公開されました」と周知することで、より多くの人の目に触れる可能性が高まります。メディア関係者だけでなく、自社のファンやフォロワーにも同じタイミングで情報を届けることで、拡散の起爆力を上げることができます。
4-2. SNSでのリアクションをプレスリリースに活かす
SNS上のユーザーからの反応やフィードバックを拾い上げ、次回以降のプレスリリースや広報戦略に反映させるのも有効です。リアルタイムで意見が集まりやすいSNSの特性を活かして、情報発信をPDCAサイクルで改善していくことで、より質の高いプレスリリースを作成できるようになります。
4-3. プレスリリース内容をSNS向けに再構成する
プレスリリースは長文で詳細な情報をまとめる傾向がありますが、SNSでは短い文章や視覚的な要素(画像や動画)がより好まれます。そこで、プレスリリースをベースにしながら、SNSごとの特性に合わせて情報を加工して発信するという手法が有効です。このように「オフィシャル情報+SNS拡散」という組み合わせを行うことで、メディアとエンドユーザー双方へアプローチが可能となります。
5.プレスリリースを活かすためのポイント
プレスリリースが「意味ない」と言われる最も大きな原因の一つは、内容が陳腐化していたり、ニュース性が乏しかったり、配信先の選定が適当になっていたりすることにあります。単に「出しておけば良い」という形だけのリリースでは、当然のことながらメディアは取り上げてくれませんし、SNSでの拡散も期待できません。以下のような改善ポイントを押さえることで、プレスリリースを“活きた情報源”に変えることが可能です。
5-1. ニュースバリューをしっかりと見極める
プレスリリースの本質は、「メディアが報道したくなる新しさや社会的意義を持つ情報を提示すること」です。企業にとってはどんな出来事も重要かもしれませんが、第三者であるメディアや読者から見たときにどのような価値があるのかを再確認しましょう。例えば、「業界初」「画期的な技術」「顧客にとって大きなメリット」などの要素があれば、ニュースバリューが高まります。
5-2. 誰に読まれるのかを明確にする
プレスリリースを配信する際には、ターゲットとなるメディアの属性や読者層をしっかり意識する必要があります。例えば、IT系の新サービスを発表するのであれば、IT系メディアやテック系ブログ、あるいはビジネス向けのニュースサイトを中心に配信するなどの戦略が必要です。闇雲に大量配信するのではなく、狙いたいメディアにピンポイントでアプローチすることが結果的に掲載率を高めます。
5-3. わかりやすく、簡潔にまとめる
どれだけニュース性があっても、文章が長ったらしく複雑だったり専門用語ばかりで伝わりにくかったりすると、読む側は内容を把握しづらくなります。プレスリリースはあくまでも“情報を的確に伝える”ためのツールであり、広報の自己満足の場ではありません。見出しやリード文で要点をつかみやすくし、本分も適切な段落や箇条書きを使って要点を整理して伝えることが重要です。
5-4. インパクトのあるビジュアルやデータを活用する
文章だけではなく、写真やグラフ、インフォグラフィックスなどのビジュアル素材を積極的に使いましょう。メディア関係者も、視覚的なインパクトがあると記事化しやすくなります。また、データや統計情報を示すときは信頼できるソースを明記することで、リリースの説得力が増します。
5-5. 配信後のフォローアップを欠かさない
プレスリリースを出して終わりではなく、配信後にメディアや記者からの問い合わせに素早く丁寧に対応することで、掲載につながる可能性が高まります。興味を持ってくれたメディアがあれば、追加情報や写真を提供するといったフォローを行い、関係性を深めておくと次回以降の広報活動にもプラスに働きます。
6.SNS時代だからこそプレスリリースが活きるケース
SNSが普及した今でも、むしろSNS時代だからこそプレスリリースが活きるシチュエーションも存在します。例を挙げてみましょう。
6-1. 危機管理・リスク対応時
不祥事や事故などの緊急時にこそ、正確でオフィシャルな情報を迅速に発信する必要があります。その際、SNSだけでなくプレスリリースも併用することで、メディアや関係各所への信頼性を担保することができます。SNSは即時性に優れますが、文字数や情報量の制限があり、誤解が生じやすい場合もあるため、長文で公式見解をまとめるプレスリリースは有効です。
6-2. 重大な経営判断や業界への影響が大きい発表
大型の資金調達や新技術の特許取得といった、業界にインパクトを与えるような内容の場合、メディアの反応も大きくなる可能性があります。SNSで軽い調子で発信するだけではその価値が伝わらないケースも多いため、プレスリリースとして正式に情報を整理し、メディアに訴求することが効果的です。
6-3. 公的機関や行政と連携する取り組み
社会的意義が大きいプロジェクトや行政との連携施策については、プレスリリース形式の告知が一般的です。行政機関や自治体がからむ案件は信頼性を重視されるため、公式発表としての体裁を整えたリリース文書が求められやすいのです。
7.プレスリリースを取り巻く今後の展望
SNSの進化は止まらず、次々と新しいプラットフォームや機能が登場しています。一方で、既存のマスメディアの影響力も依然として大きく、特定の読者・視聴者層に対しては絶大なリーチ力を誇ります。企業や団体が持つ広報手段は、プレスリリースやSNS、オウンドメディアなど多岐にわたるようになりました。今後はこれらのツールを組み合わせながら、最適な方法で情報を発信できるかどうかが鍵となるでしょう。
- マルチチャネル化: プレスリリースは今後も一定の役割を担いながら、SNSや自社ブログ、動画配信サービスなど複数のチャネルを併用する形が主流になる。
- データ重視の広報: PRの世界でもデータドリブンな意思決定が求められ、リリース配信の効果測定やSNSでのエンゲージメント分析をもとに最適化が進む。
- スピードと信頼性の両立: SNSのスピードとプレスリリースの公式性・信頼性をいかに組み合わせるかが、広報戦略の成否を左右する。
8.結局、プレスリリースって意味がないの?必要あるの?
本記事では、「プレスリリースは意味がない」という主張を一面的にとらえるのではなく、なぜそう言われるのか、そして実際にはどんな価値があるのかを解説してきました。結論として、プレスリリースは決して時代遅れの無用の長物ではありません。しかし、従来のようにただ出すだけで十分な効果が得られる時代でもなくなったのは確かです。
SNSが普及し、情報発信の在り方が大きく変化した現在だからこそ、プレスリリースの本質的な役割を見直し、より戦略的な運用が求められています。自社の商品やサービス、あるいは活動内容について、本当にニュースとしての価値があるのかを吟味し、メディアが求める情報を的確に提供する努力が不可欠です。また、プレスリリースとSNSを組み合わせた“ハイブリッド型広報”を行うことで、双方の強みを引き出すこともできます。
9.プレスリリースを効果的に活用する具体的なステップと実践例
ここからは、プレスリリースが「意味がない」と言われる状況を打破し、SNS時代でも活きるプレスリリース運用を行うための具体的なステップと、実践例をさらに詳しくご紹介いたします。
9–1. 目的とゴールの設定
まずは「プレスリリースを活用して何を達成したいのか」を明確化することが不可欠です。新商品や新サービスの発売を告知したいのか、ブランドイメージを向上させたいのか、あるいは専門メディアに取り上げてもらうことで信頼性を高めたいのか。目指すゴールによって、文章のトーンや構成、配信先の選定が大きく変わります。
- 例: スタートアップ企業が大手企業との資本業務提携を発表し、投資家や業界関係者にアピールしたい場合、プレスリリースでは提携の意図や業界へのインパクト、今後の展望などをしっかりと盛り込みましょう。
9–2. 事実情報とストーリー性の両立
ただ情報を羅列するだけでは、メディアもユーザーも興味を示しにくいです。新しい取り組みや商品であれば「開発の背景」「ユーザーが感じるメリット」などのストーリーを加えると、読み手に引き込まれるきっかけを作れます。一方で、客観性を保つためにも事実関係やデータをしっかりと示すことが大切です。
- 例: ユニークな経緯で誕生した商品があるなら、その裏側のエピソードや社内での苦労、ユーザーインタビューなどを盛り込みつつ、データや具体的成果を添えて説得力を高めます。
9–3. メディア・記者の視点でリリースをチェック
プレスリリースは“書き手”中心ではなく、“読み手”中心である必要があります。特に記者や編集者は「読者が興味を持つか」「記事化の価値があるか」を基準に情報を判断します。専門用語や社内用語が多いと、それだけで敬遠される可能性があります。キャッチコピーやタイトルの付け方、本文の段落構成にも工夫を凝らし、ひと目で魅力的に映るようにまとめましょう。
9–4. 適切なタイミングと配信方法の選択
プレスリリースは内容だけでなく、送付するタイミングも重要です。曜日や時間帯、業界のニュースサイクルなど、メディア側が取り上げやすいタイミングをリサーチし、配信スケジュールを組むと効果的です。さらに、配信方法としては、「自社で保有するメディアリストへの直接メール」「プレスリリース配信サービス」「SNSでの同時告知」などを併用することで、より幅広い層にリーチできます。
9–5. メディア掲載後・未掲載時のアクション
プレスリリースを配信した後、取り上げてくれたメディアがあれば感謝の意を伝え、今後も情報交換を続けることで関係性を構築すると良いでしょう。未掲載の場合でも、内容を精査し、どの部分が魅力に欠けていたのかを検証し、次回のリリースに活かします。なお、まったく取り上げてもらえなかったリリース内容でも、SNSや自社サイトでユーザーとのコミュニケーションに活用する道は残っています。
【実践例:地方の小規模企業がプレスリリースで全国進出のきっかけを掴む】
ある地方の小規模食品メーカーは、SNSで地元のファンを獲得していたものの、全国的な知名度は低い状態でした。しかし、新商品の発売を機にプレスリリースを作成し、大手食品系ニュースサイトや地域活性化に関心の高いメディアへ重点的にアプローチを行ったところ、複数のオンラインメディアで取り上げられ、一気に全国区の注文数が増加したという事例があります。SNSだけでは届かなかった層にアピールできたのは、プレスリリースを通じて公式感ある情報を的確に届けられたことが大きな要因でした。
【実践例:テック系スタートアップが社会問題と絡めて話題化】
テクノロジー関連のスタートアップは、新技術の社会的インパクトを伝えやすいという強みがあります。例えば、AI技術を活用して高齢者の生活を支援するサービスを開始した会社があったとして、その企業はプレスリリースで「少子高齢化社会への対応」「地域医療との連携」「高齢者の生活の質向上」といった社会的意義を前面に打ち出しました。すると、一般的なIT系メディアだけでなく、社会問題や介護分野に関心の高いメディアや新聞社からも問い合わせが入り、結果的に大きく露出機会を増やしました。このように、SNS投稿では伝えきれない要素をプレスリリースでしっかりまとめたことが成功要因となったのです。
【実践例:危機対応時にプレスリリースでブランド価値を守る】
ある企業が製品に関する不具合を公表せざるを得なくなった際、SNSだけでは誤解が生じる恐れが高いと判断し、プレスリリースを介して公式見解を発表しました。具体的な対応策や再発防止策、連絡先を明確に提示し、迅速かつ丁寧な説明を行うことで、大きな炎上やブランドイメージの失墜を最小限に抑えられたと言われています。これはプレスリリース特有の公式性と情報整理力が功を奏した事例の一つです。
プレスリリースは時代遅れではなく、進化する広報ツールの一翼
「プレスリリース 意味ない」というキーワードが示すように、SNSやデジタルメディアが大きく発達した現代において、プレスリリースを活用する意義を疑問視する声は確かに存在します。しかし、その背景には「プレスリリースの形骸化」や「配信目的のあいまいさ」「メディアとのコミュニケーション不足」といった課題が潜んでおり、これらを改善・最適化すれば、プレスリリースは今なお有効な広報手段であり続けるのです。
むしろSNSが主流となった今だからこそ、プレスリリースがオフィシャル情報としての重みを増す場面も多々あります。SNSとプレスリリースは対立するものではなく、正確な情報を伝えるための公式文書としての位置づけと、ユーザーとの双方向コミュニケーションを可能にするSNSの特性が相互に補完し合うのです。
もちろん、現代の情報発信ではスピード感が求められますし、一瞬で膨大な情報が流れ去るSNSの世界で注目を集めるのは容易ではありません。しかし、だからこそ“伝えるべき内容”をしっかり練り上げ、最適なタイミングで、最適な手段を使って伝えるという基本を再確認する必要があります。
プレスリリースが本当に意味を持たなくなるのは、それを使う側が目的意識を失い、内容のクオリティや配信戦略をおろそかにする時だけです。SNS全盛の時代にあってもなお、プレスリリースには独自の強みと役割があります。時代に合わせて進化し続ける広報ツールとして、今後も注目されることでしょう。
もし「プレスリリースは意味がないのでは?」と感じているのであれば、本記事で紹介したポイントをもう一度チェックし、現代のメディア環境とSNSユーザーのニーズを踏まえた新しい運用スタイルを試してみることをおすすめします。うまくはまったとき、SNSの拡散力とプレスリリースの信頼性が掛け合わさることで、想像以上の大きな成果を生み出せる可能性が広がっています。
最後に
SNS時代における情報発信は非常にダイナミックであり、変化が早い世界です。1年前には効果的だった施策が、今ではあまり通用しなくなっていることも珍しくありません。そうした環境の中で、「プレスリリースはもう意味がない」と一刀両断にしてしまうのは早計と言えるでしょう。むしろ、SNSだけでは補えない部分をプレスリリースが担える可能性は十分にあります。
大切なのは、常に学びと改善を繰り返しながら、自社の広報目的やターゲットメディアに合わせた最適な手段を選択していくことです。プレスリリースが本質的に果たすべき役割、そしてSNSが得意とする部分、それぞれを理解し、上手に組み合わせることで、今後の広報活動はより強力なものへと進化していくことでしょう。
プレスリリースが「本当に意味がないのか?」ではなく、使い方や考え方次第で、その効果は大きく変わってくるのです。SNSと競合するどころか、むしろ補完関係にあると捉え、企業や団体が社会に向けて正しく情報を発信し、多くの人々と豊かなコミュニケーションを築いていくための武器として、引き続き上手に活用していきましょう。
以上、プレスリリースが「意味がない」と言われる背景と実際の価値、新時代のPR戦略においてどう活かしていけるのかについて総合的に解説しました。今後の広報・PR活動において少しでも参考になれば幸いです。